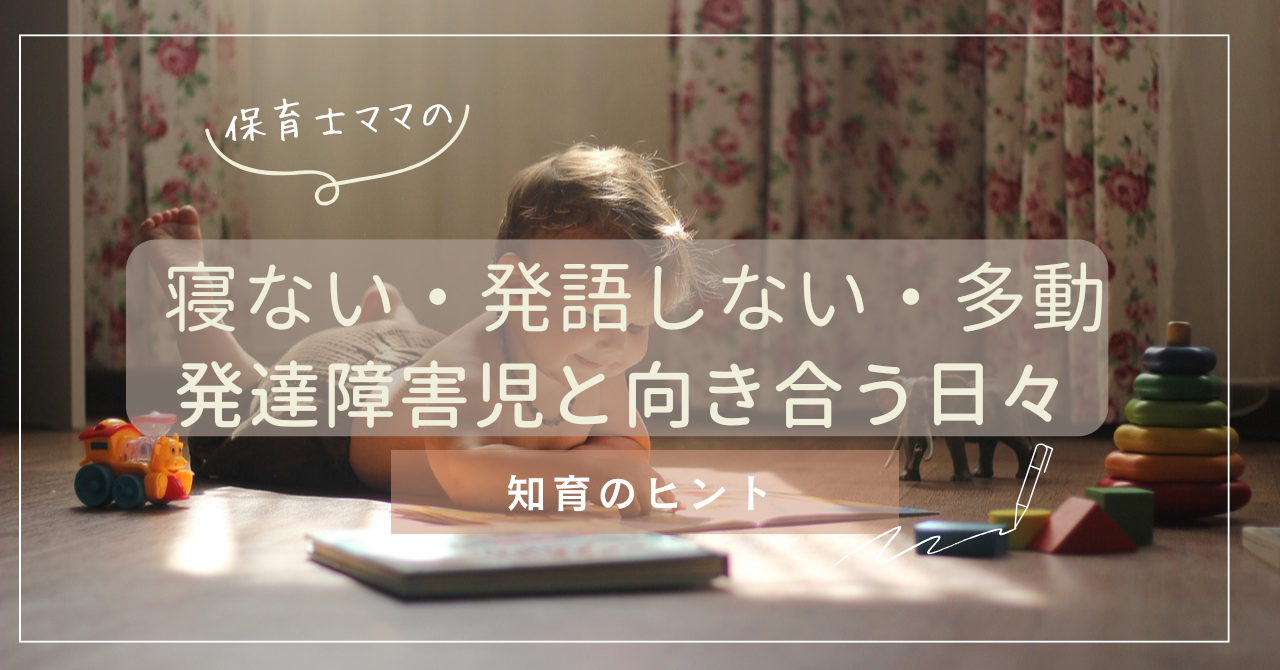私は保育士として多くのお子さんたちを見てきました。
子育ての楽しさや大変さはもちろん知っていましたし、仕事を通じて多くの知識も持っていたつもりです。
しかし、実際に我が子を育てるとなると、理論や経験では解決できない「育てにくさ」に直面することが多くありました。
ASD・ADHDと診断された息子の育児では、特にその難しさを痛感しました。
ここでは、その体験をいくつかの項目に分けてお伝えします。
気になる部分があれば、ぜひご覧ください。
寝ない!一番悩んだこと

私は保育士として、赤ちゃんの睡眠に関しても知識を持っていましたが、息子の睡眠は私にとって大きな課題でした。
抱っこで寝ても、布団に置いた瞬間に目を覚ます。
これまでの仕事でも「背中スイッチ」のような現象はよく聞いていましたが、自分の子どもでこれほどまでに頻繁に経験するとは思いませんでした。
保育士として、子どもが安心できる環境づくりがいかに大切かを知っていたため、息子にも生後3か月ごろから自立入眠の練習を始めました。
お腹や足を撫でながら、優しい声をかけて眠りに導こうと試みたのです。
最終的には添い寝で眠れるようになり、少し負担が減りましたが、根本的な解決には至りませんでした。
次に悩んだのは、『夜中に何度も目を覚ますこと』でした。
どれだけ工夫しても、息子の眠りは短く、30分から1時間ごとに目を覚ます毎日が続きました。
夜が来るのが怖くなるほどで、毎晩強いストレスを感じていました。
冬の寒い時期には、パジャマや布団、室温の調整にも細心の注意を払いながら試行錯誤を繰り返しましたが、効果は見られませんでした。
こうした状態が、生後10か月まで続きましたが、大きな転機が訪れたのは、離乳食が順調に進み、夜間の授乳がなくなったときでした。
授乳の必要がなくなったことで、夜中に目を覚ます回数がぐっと減り、初めて4時間連続で眠ってくれた瞬間を今でも覚えています。
その後も、夜中に一度起きても、体を軽く撫でるだけで再び眠れるようになり、息子の睡眠時間が少しずつ安定していきました。
保育士として、赤ちゃんには個人差があることを十分に理解していましたが、やはり自分の子どもとなると特効薬のような解決策はなく、途方に暮れることもありました。
しかし、試行錯誤を通じて少しずつ効果のあった対策については、また別の記事で詳しくご紹介したいと思います。
人見知りも場所見知りもしない!いつもニコニコ

保育園では、人見知りや場所見知りをする子どもたちをよく目にしますが、息子はその逆でした。
これまで一度も人見知りをしたことがなく、むしろ人が大好きで自ら積極的に関わろうとします。
赤ちゃんの頃から、知らない人にもニコニコ笑顔を振りまき、私が見えなくなってもまったく動じない姿には驚かされました。
絵本が大好きで、物を整列させるのが得意

保育士として、子どもたちに絵本を読み聞かせる時間はとても大切だと感じていましたが、息子の場合はそれ以上に絵本が大好きでした。
赤ちゃんの頃から一番興味を示したのは絵本で、特に写真がたくさん載っている図鑑や、乗り物や電車に関する絵本を好みました。
息子は一人でじっと絵本を見ている時間が長く、その集中力には感心するばかりでした。
さらに興味深かったのは、息子が物を整然と並べることが好きだったことです。
ミニカーや新幹線の模型を一列に並べて、その様子を眺めたり走らせたりする姿をよく見かけました。
保育園でも、おもちゃを並べることに夢中になる子どもたちはいますが、息子の場合は特に並べ方にこだわりが強く、絵本やカップなど、何でもきれいに整列させて遊んでいました。
四角い重ねカップを積むときにも、ただ積み上げるのではなく、角や絵柄をきちんと揃えて積み上げる姿は、彼なりの独自のルールに基づいて遊んでいるように見えました。
目や手を一瞬でも離すと危険!

息子はとても活発で、体力があり、常に動き回っていました。
保育園では活発な子どもたちを見慣れていますが、息子のエネルギーはそれ以上で、「こんなに寝不足なのに、どうしてこんなに元気でいられるんだろう?」と感心してしまうほど。
自宅では、息子が安全に遊べるように家具を固定し、危険な場所にはパーテーションを設け、自由に動き回れる環境を整えました。
しかし、外に出るとその対策は通用せず、息子は周りの状況を気にせずに走り出してしまうことがよくありました。
一度も振り返らず、どこまでも走っていってしまうため、目を離すことは命に関わる危険を伴いました。
特に荷物を持ち替える一瞬の隙で手を離すと、その瞬間にいなくなってしまうことがあり、外出は常に緊張の連続でした。
今でもその傾向は続いているため、外出時には声をかけながら、安全に移動するための練習を続けています。
視線を合わせない、発語が少ない、真似をしない、食べムラがある

保育士としての経験から、子どもの発達については個人差など考慮しても敏感に感じ取ることができると思っていましたが、息子に関しては思わぬところで指摘を受けました。
1歳半検診で「声をかけても視線が合わない」「動きが多い」「発語がない亅といった点を指摘されたのです。
保育園でも、発達のスピードには個人差があることは承知していましたが、息子が意味のある発語をほとんどしないことや、こちらから声をかけても反応が乏しい点など改めて注意を払うようになりました。
また、息子は他の人の動作を見ていても真似をすることがなく、食事にもムラが出てきました。
市の子育て支援センターに参加している、同じ年齢の子どもたちの行動と比べると、その違いが目立つようになり、私は「この子には何か発達の面で支援が必要かもしれない」と感じ、一歳半検診を機に市の相談機関に行くことを決めました。
保育士としての経験を活かして育児をしていますが、自分の子どもを育てる中で、新たに学ぶことや考えさせられることがたくさんあります。
これからも、その経験をシェアしながら同じような悩みを持つ方々の力になれればと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
次回は、息子の身体的な成長について、さらに詳しく書いてみたいと思います。息子の発達に伴う悩みや工夫、そして感じた成長の喜びについてお話しします。