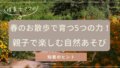子どもの時間管理を教えるのは、本当に大切なことです。
でも、時間っていうのは抽象的なもので、子どもに伝えるのが難しいこともあります。
そこで、知育時計やスマートフォンアプリを使ってみてはいかがでしょうか?
この記事では、楽しく時間管理を学べる知育時計とおすすめのアプリを紹介します。
どの年齢の子どもでも使いやすい方法や、実際に家で試せるアイデアもたくさん紹介します。
子どもと一緒に「時間」を楽しく学んで、将来のために大きなステップを踏み出してみてください!
子どもと一緒に楽しく時計を学ぼう!おすすめアプリ紹介
ゲームみたいに楽しく時計を覚えるアプリ
 出典:さわってわかる時計の読み方
出典:さわってわかる時計の読み方
【特徴】
✔️ 時計の針を操作することで、音声で時間を教えてくれる機能を備えたアプリです。
✔️ クイズ形式で楽しく時計の読み方を学べるようになっていて、難易度を選択できるため、どんな子どもでも楽しむことができます。
【使い方】
✔️ 時計の針を自由に動かして時間を確認したり、クイズ形式で正しい時間を答えることができます。
✔️ 難易度を調整しながら、少しずつ難しくしていくことができるので、楽しみながら時間の学習ができます。
 出典:学研さんすうランド
出典:学研さんすうランド
【特徴】
✔️ 数字の書き方や数の大小、時計の読み方、簡単な計算(足し算や引き算)などを学べる知育アプリです。
✔️ ゲーム形式で楽しく学べるようになっており、子どもの成長に合わせて進められる内容になっています。
【使い方】
✔️ 子どもがアプリを操作して、数字や計算を学習したり、ゲーム形式で問題を解決することができます。
✔️ 子どものペースで進められるため、楽しみながら少しずつ難しくしていくことができます。
時間の流れが目で見てわかるアプリ
 出典:ルーチンタイマー
出典:ルーチンタイマー
【特徴】
✔️ 毎日のルーチンを設定し、音声でガイドしてくれるアプリです。
✔️ 朝の準備や家事など、時間管理をサポートしてくれます。
【使い方】
✔️ 朝の準備やお昼ごはんの時間など、やりたいことを登録しましょう。
✔️ ボタンを押すと音声で案内してくれるので、忘れずに進められます。
✔️ 一時停止やスキップもできるので、自分のペースで使えますよ。
毎日の習慣づけをサポートするアプリ
 出典:Dodo
出典:Dodo
【特徴】
✔️ 家族全員で利用できるタスク管理アプリです。
✔️ 大人と子どもで役割を分けて進められ、終わったらお互いに頑張りを認め合えます。
【使い方】
✔️ Dodoアプリは、家族でアカウントを作成し、タスクを登録して使います。
✔️ タスク完了後に「おわった!」ボタンを押せば、家族に報告でき、頑張りを評価してもらえるのでモチベーションもアップします。

知育時計と一緒にアプリを使うと、子どもはもっと楽しく時間の感覚を学べます。
年齢や理解度に合わせて選び、日常生活で取り入れてみてくださいね!
子どもの年齢に合わせた時計の教え方
3~4歳:時計と仲良くなろう!
この年齢の子どもには、時計を身近に感じてもらうことが大切です。
✔️ おもちゃの大きな時計で遊ぼう
針を動かしたり、数字を指さしたりして楽しく遊びます。
✔️ 生活の中で時計を見る習慣をつけよう
「おやつの時間だよ」「お風呂の時間だね」など、日常の出来事と時計を結びつけて声をかけます。
5~6歳:時計の読み方の基本を学ぼう
少しずつ時計の読み方を教えていきます。
✔️ まずは短い針(時針)から
「短い針が2を指してるね。2時だよ」と教えます。
✔️ 次に「ちょうど」と「30分」
「3時ちょうど」「3時30分」など、わかりやすい時刻から始めます。
✔️ 最後に長い針(分針)
「長い針が1のところにあるから5分、2のところにあるから10分」というように、5分刻みで教えていきます。
小学生:時間の使い方を学ぼう
時計が読めるようになったら、時間の使い方を考える練習をします。
✔️ 「あと何分」を意識しよう
「10分前」「1時間後」など、時間の前後関係を学びます。
✔️ 1日の予定を立ててみよう
「学校から帰ってきたら、おやつを食べて、宿題をして、お風呂に入る」など、簡単な1日の予定を自分で考える練習をします。

このように、子どもの年齢に合わせて少しずつ時計や時間の概念を教えていくことで、楽しみながら時間管理の力を身につけることができます。
手作りと市販の時計で楽しく時間を学ぼう!
自作時計で時間の基本を遊びながら覚える
家にあるものや100均の材料で作れる手作り時計は、子どもにぴったりの学習ツールです。
 必要な絵カードと合わせれば、子ども特製の時計になりますよ。
必要な絵カードと合わせれば、子ども特製の時計になりますよ。
例えば、ダイソーの「壁掛け時計」の文字盤を少し工夫すれば、長い針と短い針が一緒に動く本格的な知育時計になります。
これで、時間がどう進むのか、針がどう動くのかを目で見て分かりやすく学べますよ。
知育時計の作り方〜活用の仕方などをカスタマイズについて紹介した記事はこちらです。
一度覗いてみてくださいね!
合わせて読みたい
知育時計で子どもの時間感覚を育てる!親子で楽しむ自作方法
「くもんのくるくるレッスン」で時計読みをマスター
手作り時計で基本を学んだら、私は次に「くもんのくるくるレッスン」を使って時間の管理方法などを伝えていきました。
この時計は、長い針と短い針の色が違って、子どもが時刻を読みやすくなっています。
自分で針を動かして、時間の流れを感じながら学べるので、楽しみながら動かして覚えていました。
 赤のレバーを上下させることで、針がさしている時間を見れます。
赤のレバーを上下させることで、針がさしている時間を見れます。
また、窓に正しい時刻が表示されるので、遊びながら時間の進み具合を確認できますよ。
この時計を使うことで、時間の正確な読み方を覚えて、時間の感覚が一緒に身についたようです。
 文字盤も細かいメモリ版とシンプルなものと2種で入れ替えることができます。
文字盤も細かいメモリ版とシンプルなものと2種で入れ替えることができます。
くもんのNEWくるくるレッスンは、楽しく学びながら時間の大切さや計画的に時間を使う力も育めるので、生活にも役立つスキルが身につきます。
日常生活で時計を使ってみよう
1. スケジュール作り
手作り時計を使って、「〇時になったら何をするか」を親子で一緒に決めてみましょう
その後、くもんのNEWくるくるレッスンで正しい時刻を確認すると、予定通りに動く練習ができます。
毎日の流れが分かると、子どもも安心して過ごせますよ。
2. 時間クイズ
「30分後は何時?」など、時計の針を動かしながらクイズを出すと、時間の感覚を楽しく身につけられます。
最初は「〇時ちょうど」から始めて、少しずつ「〇時30分」「〇時15分」とレベルアップしていくと、自然に時間の計算ができるようになりますよ。
3. 生活の中で使う
「3時になったらおやつだね」「8時になったら寝る時間だよ」と声かけしながら時計を確認する習慣をつけましょう。
日常生活の中で繰り返すことで、子どもは自然と時間を意識するようになり、生活リズムも整いやすくなります。

毎日の生活の中で少しずつ練習していけば、時間管理の力が自然と育っていきますよ。
知育時計とくるくるレッスンの良いところを合わせ持つアイテムもあります。
【学研の遊びながらよくわかる とけいのレッスン】
✔️ 本物の時計と目標時計の組み合わせ
「ほんもの時計」と「もくひょう時計」の2つを見比べることで、時間の流れや目標設定を視覚的に理解できます。
✔️ ホワイトボード機能付き目標時計
「もくひょう時計」の盤面がホワイトボードになっているため、自由に目標時間や予定を書き込むことができます。
✔️ 時間と分の読みやすさ
両方の時計の盤面が【時間】と【分】を読みやすいように工夫されており、子どもでも理解しやすいデザインになっています。
✔️ 生活習慣の意識づけ
目標時間を設定し、それに向けて時間を意識することで、規則正しい生活習慣を身につけることができます。
✔️ 長期間使用可能
3歳頃から小中学生まで長く使えるため、子どもの発達に応じて時間の概念や管理能力を育てることができます。

時計の読み方を学ぶだけでなく、生活習慣の定着にも役立つ知育アイテムです。
親子で楽しみながら、自然と時間の感覚が身につきます。
子どもと一緒に楽しく時間管理!簡単タイムマネジメントのコツ
大切なことから順番に:やることリストの作り方

子どもと一緒に、その日にやることをリストにしてみましょう。
例えば、宿題、おやつ、お風呂、寝る時間などです。
そして、「今すぐやらないといけないこと」と「後でもいいこと」に分けます。
これで、何を先にすべきか分かりやすくなります。
時計を見ながら声かけ:次の行動を予告しよう

「あと10分でおやつの時間だよ」「長い針が6になったら、お風呂に入ろうね」など、時計を見ながら次の行動を伝えましょう。
これを繰り返すことで、子どもも自然と時間を意識するようになります。
アナログとデジタル、両方の時計を使おう

壁掛けの針のある時計(アナログ時計)で大まかな時間の流れを、スマホやデジタル時計で細かい時間を確認する習慣をつけましょう。
アナログ時計は時間の流れが目で見て分かりやすく、デジタル時計は今の時間がすぐに分かります。
両方使うことで、時間の感覚がより身につきます。

これらの方法を日常生活に取り入れることで、子どもも楽しみながら時間管理のコツを学べます。
焦らず、少しずつ習慣にしていきましょう。
知育時計の選び方とおすすめアイテム
子どもが時計を読めるようになると、時間の流れを理解し、自分でスケジュールを管理する力が身につきます。
そんな成長をサポートする「知育時計」の選び方や、おすすめ商品をご紹介します!
人気の知育時計3選
1.セイコークロック「掛け時計 知育 アナログ」
時針と分針がそれぞれ異なる色で表示されているため、どの針が「時」や「分」を指しているかが一目でわかります。
また、1分単位で数字が書かれているので、細かい時間の読み方も練習できます。
2.MAG「知育時計よ~める」
壁掛けタイプや目覚まし時計、防水タイプなど種類が豊富。
特に、ひらがなで使い方が書かれているモデルは、小さな子どもでも自分で操作しやすく、親子で楽しく学べます。
3.くもん出版「スタディめざまし」
針が指している数字を読むだけで時刻を確認できるシンプルな設計。
学習用に特化しており、小学校の授業でも役立つアイテムです。
知育時計選びの4つのポイント
1.年齢に適した機能を選ぶ
小さな子どもには、短針・長針が色分けされているものや、大きな文字盤の時計がおすすめ。
成長に合わせて、デジタル表示やアラーム機能付きのものにステップアップしましょう。
2.デザインと見やすさ
子どもが興味を持つデザインや好きなキャラクター入りの時計は、学ぶ意欲を引き出します。
また、文字盤が見やすく、針がはっきり区別できるものを選ぶと、理解しやすくなりますよ。
3.耐久性と安全性
子どもが頻繁に触ったり落としたりすることを考慮して、安全な素材(プラスチック製など)や壊れにくい設計のものを選びましょう。
4.追加機能もチェック
アラーム機能やタイマー機能付きの時計は、時間管理の練習にも役立ちます。
例えば、「あと5分でお片付けしようね」といった声かけと合わせて使うことで、時間感覚を養えます。
【子どもに合った知育時計を選ぼう!】
知育時計はただ時間を教えるだけでなく、子どもの成長に合わせてスケジュール管理や時間感覚を楽しく身につけられるツールです。
今回ご紹介した商品や選び方のポイントを参考に、お子さんにぴったりの知育時計を見つけてみてくださいね!
子どもの成長を支える知育時計の活用法
知育時計とアプリを一緒に使うと、子どもが楽しく時間の感覚を学べます。
年齢や興味に合ったものを選んで、日常生活や勉強に取り入れると、自然と時間管理の力が身につきますね。
手作りの知育時計と「くもんのくるくるレッスン」を組み合わせると、基礎から応用までバランスよく学べるので、より効果的です。
日常に取り入れることで、遊びながら時間の感覚を育てる環境が作れます。
ぜひ、お子さんに合った方法で楽しく学ぶ時間をサポートしてみてくださいね。
合わせて読みたい
知育時計で子どもの時間感覚を育てる!親子で楽しむ自作方法
合わせて読みたい
子どもの時間管理力を育む!知育時計の選び方と楽しい活用法