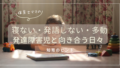身体の大まかな発達歴
 息子の実際の身体の発達の記録です。何かの参考になれば…と提示します。
黒字は息子の数値です。
※()内の数字は赤ちゃんの発達における平均的な月齢
息子の実際の身体の発達の記録です。何かの参考になれば…と提示します。
黒字は息子の数値です。
※()内の数字は赤ちゃんの発達における平均的な月齢
| 首の座り:4ヶ月(3〜4ヶ月) | 寝返り:5ヶ月(4〜6ヶ月) |
| ずり這い:7ヶ月(7〜9ヶ月) | 座位:9ヶ月(7〜9ヶ月) |
| つかまり立ち:9ヶ月(8〜9ヶ月) | 伝い歩き:10ヶ月(9〜1歳頃) |
| はいはい:1歳(8〜10ヶ月) | 歩き始め:1歳4ヶ月(12〜15ヶ月) |
これを見ると、通常の発達と比べて少しのんびりした項目もありますが、私は「ゆっくりだけど、この子のペースで成長しているから問題ない!」とあまり深く考えていませんでした。
しかし、身体の使い方について「どうしてだろう?」と感じることがありました。
それは、ずり這いができるようになってからのことです。
身体の成長についての気づき

息子を連れて月に数回、市が主催する子育て支援センターに通っていました。
そこは広々としたフラットなフローリングの空間で、息子を下ろすと、ほとんど腕の力だけでずり這いをしながら進み、慣れてくると腕と脚を交互に動かして自由に移動し、楽しんでいました。
一方で自宅では、転倒防止のためにプレイマットや絨毯を敷いていたため、息子はずり這いでは進めず、寝返りを繰り返して目的地まで辿り着く方法で移動していました。
私は「ずり這いが上手になってきたから、そのうちはいはいに移行するだろう」と思っていたのですが、つかまり立ちや伝い歩きが始まっても、はいはいには移行しませんでした。
その当時は「どうしてはいはいをしないんだろう?」と疑問に感じていましたが、今になって分かることは、「しない」のではなく「できなかった」のだということです。
腕で上半身を支え、お腹を床につけずにはいはいするための体幹発達が追いついていなかったため、息子はずり這いで移動していたのです。
私はそのことに全く気づいていませんでした。
戸惑いと期待

保育士として、赤ちゃんの成長過程を見てきた私は、息子の成長にもある程度の「基準」を持っていました。
例えば、寝返りやはいはい、歩き始めるタイミングにはある程度の目安があり、それぞれの子どもに個人差があることも理解していました。
だからこそ、息子がずり這いを始めた時は、「きっともうすぐはいはいに移行するだろう」と自然に思っていたのです。
保育士としての経験があったため、焦ることなく「この子のペースで成長すれば良い」と思っていました。
しかし、つかまり立ちや伝い歩きが始まっても、息子はなかなかはいはいをしませんでした。
その時の私は戸惑いを感じましたが、保育士としての知識がある分、「少し遅れているだけかもしれない」と自分に言い聞かせ、あまり心配しないように努めていました。
育児をしている中で、どうしても「専門家の目線」で息子を見てしまうことがあり、「まあ個人差があるし…」と自分を納得させていたのです。
不安と気づき

それでも、不安がまったくなかったわけではありません。
市の子育て支援センターで、他の子どもたちがすいすいとはいはいをしている姿を見るたびに、どうしても息子と比較してしまうことがありました。
保育士としての経験があるからこそ、発達の「平均的なライン」や「目安」が頭にあり、息子がそのラインから少しずれていることに気づいてしまうのです。
専門的な知識がある分、そのギャップが余計に気になり、心の中では「大丈夫だろうか?」という不安が少しずつ大きくなっていきました。
「はいはいはまだしないけど、元気にずり這いをしているから大丈夫」という安心感と、「何か見落としていることはないだろうか?」という保育士としての疑念が入り混じっていました。
保育士としての知識と、母親としての感情がぶつかり合う日々でした。
保育士としての知識と母としての心情…

保育士として、多くの子どもたちを見てきた分、息子の発達については「ゆっくりでも大丈夫」と安心していた反面、どこかで「この遅れが何かのサインではないか?」と心の片隅に引っかかる感情がありました。
特に、身体の使い方に違和感を感じた時は、これが一時的な遅れなのか、もっと深い問題があるのかなと見極めるのが難しかったです。
今振り返ってみると、はいはいができなかったのは、単に「遅れている」のではなく、体幹の発達が追いついていなかったために「できなかった」のだということがわかります。
しかし、当時の私はそのことに気づかず、母親としての直感と保育士としての知識の間で揺れ動いていました。
保育士としての知識があることで、発達の段階を冷静に見守ろうとする一方で、母親としては、息子が他の子どもたちと違う部分に対して不安を抱いていました。
このような感情のせめぎ合いが、息子の成長を見守る中で常に私の中にありました。
違和感を感じたらSOSを出していい!

保育士としての経験を活かして育児をしていますが、自分の子どもを育てる中で、新たに学ぶことや考えさせられることがたくさんあります。
もし少しでも違和感を感じる事があったら、周りの人に話を聞いてもらい共有していくことが大切です。
一人でそれを抱え込むより、そうする事で保護者の気持ちも軽減されたり、解決へと導く道になる事があります。
私自身ももっと早くそれに気がつけば良かったと思っています!